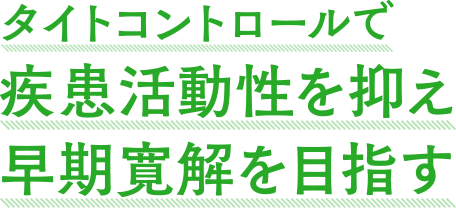先生からのメッセージ
先生からのメッセージ
- 東京都立病院機構東京都立多摩総合医療センター リウマチ膠原病科
- 医長
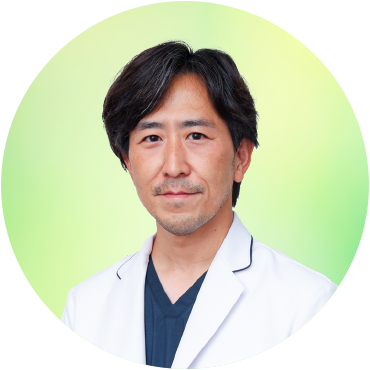
治療は主治医と相談しながら一緒に進めていく
当院の所在する多摩地域では入院診療まで行えるリウマチ・膠原病科は限られており、重症・難治性の患者さんも多く来院されるため、最後の砦という意識をもって診療に当たっています。関節リウマチと診断された患者さんは痛みの心配だけでなく、この先どうなってしまうのだろうという将来への不安を抱える方も多いです。しかし早期診断で速やかに治療を開始できれば、大部分の方は骨破壊を防ぐことができ、発病前の生活を取り戻すことができます。そのためには主治医と治療方針についてよく相談しながら治療目標を決め、主治医と一緒に治療を行っていくという意識で臨んでいただくことが望ましいと思います。
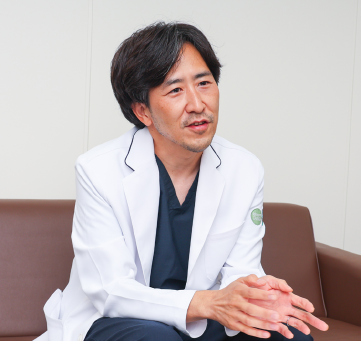
最終的に関節の腫れ・痛みがなくなることが大切
関節リウマチの治療は薬物療法が中心で、今は薬剤の選択肢も増えています。
毎回の診察では病気の勢いを示す疾患活動性を評価し、関節リウマチの状態を把握します。 疾患活動性は押して痛い関節(圧痛関節)の数、腫れている関節(腫脹関節)の数、血液検査(CRPや血沈などの急性期反応物質)、医師と患者さんの全般評価などを組み合わせたDAS28やCDAI、SDAIといった複合的評価指標を用いて評価します1)。これらの数値を活動性がない良好な状態にまで低下させることが治療目標となります。定期的にこのような複合的指標を評価して治療効果を判定しながら治療方針を見直し、早期に痛みや腫れのない寛解状態を目指していくことをTreat to Target (T2T)と呼び、近年関節リウマチの重要な治療戦略となっています2)。しかし疾患活動性が低下しても関節の腫れが残っていれば関節破壊が進行していく可能性がありますので、数値だけに捉われずに、筋骨格超音波も用いて滑膜炎が残っていないか評価することが大切です。
軽い散歩などによるADL の維持も免疫力に良い影響を与える
日常生活で大切なのは、無理をしないことです。炎症があり痛みが強くでているのに無理に体を動かすのはよくありません。しかし全く体を動かさないでいると関節が硬くなったり、筋肉が落ちて日常生活動作(ADL)が落ちてしまいます。15分程度の散歩でもよいので無理のない範囲で運動を行うことをお勧めしています。外を歩くだけでもリフレッシュしますし、抑うつ効果も期待できます。
関節リウマチ治療では薬の影響により免疫力が低下する場合があります。免疫力は患者さんの年齢や合併症、元々のADLなども関係しますので、普段からの運動でADLを維持したり、合併症をきちんと管理しておくことを心がけていただければと思います。
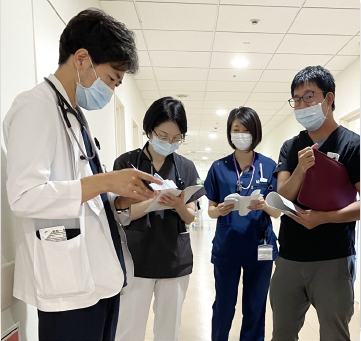
参考文献
-
1)DAS28: Disease Acitivity Score 28, CDAI: Clinical Disease Activity Index, SDAI: Simplified Disease Activity Index.
2)Ann Rheum Dis. 2010 Apr; 69(4): 631-7.
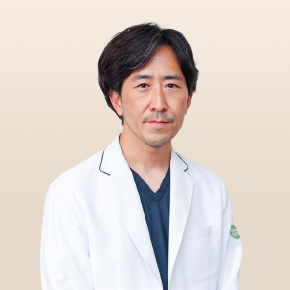
永井 佳樹 先生
2005年高知大学医学部卒業後、東京都健康長寿医療センターにて初期研修。2007年東京都立府中病院救急診療科、2008年同院リウマチ膠原病科にて後期研修。2010年東京都立多摩総合医療センターリウマチ膠原病科医員。2017年多摩北部医療センターリウマチ膠原病科医長。2018年東京都立多摩総合医療センターリウマチ膠原病科医長。2021年日野市立病院総合内科部長。2022年より現職。
東京都立病院機構東京都立多摩総合医療センター
病床数:756床
所在地:東京都府中市武蔵台2丁目8-29
※所属および掲載内容は、取材当時のものです。
 Page top
Page top